房小山&高塚山・その5

2013年6月9日 (日)
島田ハイキングクラブ6月の定例山行
〓 房小山 & 高塚山 〓
房小山&高塚山・その5
(最終回)
『房小山コース』 メンバーのフォト集。 (写真提供・永田y)
島田ハイキングクラブ6月の定例山行
〓 房小山 & 高塚山 〓
房小山&高塚山・その5
(最終回)
『房小山コース』 メンバーのフォト集。 (写真提供・永田y)
千石沢を詰める

山頂

山頂を後にして

私が房小山を初めて訪れたのは、99年6月、同年秋に行われる県民スポーツ祭登山大会のコース調査への参加でした。当時は訪れる人も稀な文字通りの秘峰でした。鋸山から先は、すぐ前をいく人も見えないほどの深い笹ヤブが、房小山まで三回ほどありました。
今まで見たこともないシロヤシオの群生が見事な花をつけ、息をのみました。スッキリとした明るい山頂に、深南部という言葉のイメージが変わりました。そして、この尾根の先に足を踏み入れてみたいと思いました。今、鋸山に立つ千頭山の会の道標や要所のマーキングは、この時設置されたもので、この登山大会を契機に房小山の一般ルート化が成されたのです。
以来、何度か訪れて思うことは、池田さんの「えーなー」という言葉のとおりです。その感嘆をたくさんの会員と分かち合いたく、先の15周年記念山行をはじめ幾度か会山行が企画されましたが、残念ながら未だ果たされていません。でも、じらされた分だけ感動も大きいし、よしんば到達できずとも、憧れは今まで以上に深く醸成されていきます。なに、80 歳でエベレストに登る人がいるご時世です。時間はたっぷりとあるのです。 〔元〕
会報やまびこ No195(6月号) 編集後記より抜粋
『房小山&高塚山』 に参加された会員は、一言感想を7╱20までに担当者まで。
メール又は口頭、定例会時でメモを手渡す等、どのような方法でもOKです。
SHC事務局
2013年06月25日 Posted by こだま at 20:24 │Comments(0) │定例山行
房小山&高塚山・その4
2013年6月9日 (日)
島田ハイキングクラブ6月の定例山行は、
〓 房小山 & 高塚山 〓
島田ハイキングクラブ6月の定例山行は、
〓 房小山 & 高塚山 〓
五樽沢コル分岐を下ると、林道南赤石線へ出る。

黄色い花は、

うすぎ・・うすぎナントカ・・ 忘却なり。 <(_ _)>

林道の水たまりに何やら小さな黒い集団 ・・。

おたまじゃくし。

鹿も歩く林道南赤石線

山崩れをコンクリートで固めた斜面を見あげたり

治山工事の足元を恐る恐る覗きこむ。

登山基地・山犬段へもうひと息。
高塚山コースが山犬段に到着すると、続いて、
15分後に房小山コースのメンバーが到着。 2コース共無事帰着。

〓 房小山&高塚山・その5 〓 に続く。
by トンボ
2013年06月18日 Posted by こだま at 21:18 │Comments(0) │定例山行
房小山&高塚山・その3
2013年6月9日 (日)
島田ハイキングクラブ6月の定例山行は、
〓 房小山 & 高塚山 〓
島田ハイキングクラブ6月の定例山行は、
〓 房小山 & 高塚山 〓
高塚山。 ♪ ~コバイケイソウに囲まれて昼食。

SHC定例山行の定例と言えば・・、山頂標識の前で集合写真。

SHCもう一つの定例、時間にゆとりがありさえすれば・・

そう。 ゲーム。

力をぬいて寛いで、お腹もできて、山頂を後にする。

ん? この花は?

リンゴの原木にリンゴの花?

三ッ合分岐。

五樽のコルから10分程下って南赤石林道へ。

〓 房小山&高塚山・その4 〓 に続く。
by トンボ
2013年06月16日 Posted by こだま at 21:44 │Comments(0) │定例山行
房小山&高塚山・その2
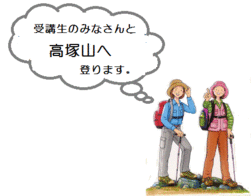
2013年6月9日 (日)
島田ハイキングクラブ6月定例山行
〓 房小山&高塚山・その2 〓
島田ハイキングクラブ6月定例山行
〓 房小山&高塚山・その2 〓
房小山組のメンバーは山犬段の小屋に前泊。朝も早立ち。今頃は汗をかいていることでしょう。

登山教室の実践山行は、
大札山、青笹山に続いて、今回が最後となる高塚山です。地形図とコンパスで山犬段から蕎麦粒山の方向を知ります。
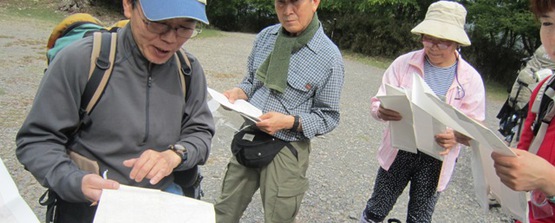
両側はスズタケに覆われた蕎麦粒山への登り

スズタケの花はよく見ると紫の地味な花。

約40分で蕎麦粒山。 標高1627m

日本一の山はうっすらと雲の中。

五樽沢コル~三ッ合~高塚山へと目指します。
セミのぬけがら

ヒメシャラ

五樽沢のコル

鹿など獣が泥をあびる ”ぬた場” をよけて歩く。

ブナの実です。

ブナの実は秋になるとクマが好んで食べるそうです。

気持ちよい山域

白ヤシオの盛りは過ぎたものの
群生しているところは葉っぱの一枚一枚に錆朱の縁どりが華やか。

体調良好!気分快適!

左に見える山が房小山。 房小山の衆に手を振ったけど見えたかな?

三ッ合に到着。

「右側の窪んでいる地形のことを ”舟窪” と言い、二つの尾根が合わさる時できます。」 と、リーダー。 説明に耳を傾ける受講生。

コバイケイソウの群生地に入ればもう山頂に着いたようなもの。

〓 房小山&高塚山・その3 〓 に続く。
by トンボ
2013年06月15日 Posted by こだま at 07:27 │Comments(0) │定例山行
房小山&高塚山・その1

2013年6月9日 (日)
島田ハイキングクラブ6月の定例山行は、
〓 房小山 & 高塚山 〓
島田ハイキングクラブ6月の定例山行は、
〓 房小山 & 高塚山 〓
先月(天城山)に続いて今月も2コースを自分で選ぶ山行。
『高塚山』 は、登山教室の最後の実施講習も兼ねての定例山行であり、 『房小山』 は、山犬段の小屋に6╱8(土)前泊、早出の健脚コース。
6╱9 15:33
山犬段駐車場。 両コースが合流し、揃って帰着の挨拶。

♪ ~ その前に
下見山行から本山行へ・・・。 ここに至るまでの経緯 ・・・
房小山は、えーなー!

房小山は、えーなー!いつ来ても、何回来ても、えーなー! 2日前、今日この日に下見することに決めて、やってきたロートル3人の素直な感想です。でも、ここに至るまでが難儀でした。当初5/11を予定していたが雨のため延期。今回は、永さんが担当の一員をかってでてくれているのだが、ご存知の通り超多忙なお方。彼女抜きで5/21にしたが、この日は3人の息が合わず、結局5/22になった。結果的にこの日で大正解。朝から素晴らしい天気に恵まれ、快適な山行ができました。 房小山は、南アルプス深南部に位置する標高1868・2mの山です。この山の魅力を語る時「明治維新の山だよ、西暦1868年と同じ標高だから」って(かえって判りにくいか)。緯度的には、青笹よりも南に在るとは意外でしょう。

林道約5㎞、山犬段1404mから約100m下ります。千石沢登り口で一息入れた後、千石沢を遡ります。下見山行に先立つ1月前(4/18)、天&池がこの沢を踏査しました。浮き石を除き、2ヶ所虎ロープを張り、要所にペンキマークを施しました。11/10SHC15周年記念山行では、手前の沢に入り込み大苦労して尾根にたどりつき、結局房小山は諦めた失敗を繰り返したくなかったからです。 千石沢のコルから房小山までの道のりは、各自地図読みして、イメージトレーニングしておいてください。

道筋には白やしおの木が沢山あります。5/22開花し始めた木もありましたが、場所によっては蕾硬く6/9頃ちょうど良い場面に出くわすかもしれません。さて、相当な距離を歩いた後、千石沢登り口から山犬段までの標高差100mを、今度は上りながら歩きます。かなり堪えるので、心してください。

一方、高塚山への道にも白やしおが沢山あります。特に、三ッ合手前の笹原の中に咲き競う白やしおは圧巻です。ここ数年、欠かさず訪れてきました。今年はどうでしょうか? 三ッ合では、リンゴの木(?)を、見つけられるかな? 一旦下降してから高塚山に至る道も好きだなぁ。登山教室の受講生も、きっと気にいってくれるでしょう。先輩としてのサポートと、好天を期待しています。 〔池〕
会報やまびこNo195(6月号) 『月々の山』 より
房小山(緑の線)下見の感想と、本番での留意点
千石沢は、ゆっくり登れば問題は少ない。濡れた岩、木の根っこには乗らない。前の人の後を追うのではなく、各自が歩きやすいところを拾っていく感じで。復路の下りは要注意。特に落石、落とさない、落としたら大声掛。千石沢中での衣服脱着はなるべくやらない。ストックはしまった方がよい。鋸山からの急降下と、それに続く痩せ尾根は要注意。1775m地点を本番では登りの最後の休憩場とするのがよい。とにかく長い、下山後、山犬段までの林道が堪える。チェックポイントを定め予定時間に通過できない方は1775m地点を目的地とする。(於、第2定例会下見報告による)
〓 房小山 & 高塚山 〓 その2に続く
by トンボ
2013年06月12日 Posted by こだま at 19:17 │Comments(0) │定例山行
2コースで歩く天城山・その6

2013年5月26日 (日)
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その6
(最終回)
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その6
(最終回)
天城縦走
(全長約17km、所要時間約7時間)のコースを踏破した健脚メンバー。

一方、石楠花コースは
天城高原GCを起終点に時計周りに万二郎岳、万三郎岳と周回し、

ゴール間近の四辻を通過したころ、・・
背中の方から、Nさんの声に似た人の笑い声が聞こえてきました。


やはりNさんでした。 ”2コース” 揃ってゴールイン!

全員無事帰着。

『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その6
(最終回)
天城山・その6
(最終回)
by トンボ
2013年06月02日 Posted by こだま at 17:00 │Comments(0) │定例山行
2コースで歩く天城山・その5

2013年5月26日 (日)
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その5
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その5
天城連山の尾根を踏破した縦走コースメンバーのフォト集。
(写真提供・O澤)
八丁池。

二つの班で行動。


小岳付近にある ”ヘビブナ” 。

まっすぐに伸びたブナと違って、くねくねとヘビのように曲がっている。

むんずと腕を組み、ヘビに巻かれないよう、しっかり女性を守ります!
こちらはシコ踏んで踏ん張っている
 ドスコイブナ。
ドスコイブナ。 

周囲に大きく根を張るブナ林の縦走路。



ブナと言えば・・・

今年の10月に計画されている、SHC特別山行は、白神岳と八甲田山。
世界遺産登録の白神山地のブナとはどんな感じだろう。と思い巡らす。

ヒメシャラとブナ。 と、ブナの幼木。

長丁場の山歩きは・・昼食時間をもうけず行動食で由とする。

休憩の都度少しづつエネルギーを補充。


この続きはまた明日・・。
♪ ~ 2コースで歩く天城山 ・ その6 に続く。
by トンボ
2013年06月01日 Posted by こだま at 20:54 │Comments(0) │定例山行
2コースで歩く天城山・その4

2013年5月26日 (日)
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その4
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その4
続いて、天城縦走コース、15名の山路を辿りましょう。
スタート地点の 水生地下(すいしょうちした)


靴のヒモはしっかり結んで。 UV対策 OK!


 何せ距離が長く、逃げ道がないから登山の途中で故障しないよう体調を整えて臨みます。
何せ距離が長く、逃げ道がないから登山の途中で故障しないよう体調を整えて臨みます。8:15 ストレッチで筋肉や股関節を柔らかくして山用の体にします。

水生地下を起点として、下り御幸歩道を通り八丁池へ、縦走路を小岳、万三郎岳、万二郎岳と進み、天城高原GCへ下ります。

それでは行ってきます。

この続きはまた明日・・。
♪ ~ 2コースで歩く天城山 ・ その5 に続く。
by トンボ
2013年05月31日 Posted by こだま at 19:17 │Comments(0) │定例山行
2コースで歩く天城山・その3
♪ ~ 続き

山登りの楽しみ方は人それぞれ。花を見たい、山でランチを楽しみたい。
私たちはそっちを選びました。(石楠花を見ながら歩く周回コース。)
 いっただっきま~す!
いっただっきま~す!
万二郎岳・万三郎岳のほぼ中間地点、石楠立(はなだて)にて昼食。
今頃、天城縦走コースの人たちは行動食で歩いているんですよね~。



おひとつ どぉ?


天城シャクナゲコースは9割が女性。

この続きはまた明日・・。

2013年5月26日 (日)
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その3
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
天城山・その3
山登りの楽しみ方は人それぞれ。花を見たい、山でランチを楽しみたい。
私たちはそっちを選びました。(石楠花を見ながら歩く周回コース。)
 いっただっきま~す!
いっただっきま~す!
万二郎岳・万三郎岳のほぼ中間地点、石楠立(はなだて)にて昼食。
今頃、天城縦走コースの人たちは行動食で歩いているんですよね~。



おひとつ どぉ?


パイナップル & よーかん
天城シャクナゲコースは9割が女性。

この写真撮影の真っ最中にワイワイガヤガヤ縦走組が到着。
この続きはまた明日・・。
♪ ~ 2コースで歩く天城山 ・ その4 に続く。
by トンボ
2013年05月30日 Posted by こだま at 17:30 │Comments(0) │定例山行
2コースで歩く天城山・その2
♪ ~ 続き

今年は石楠花シーズンの裏年にあたるそうで花芽が少なく開花も早め。 ギリギリ、最後のシャクナゲが見られました。



「あそこにいっぱい咲いているのにね。」

登山道脇のやさしい薄桃色の花弁が疲れを癒してくれる。

ヒメシャラやアセビの自然林に囲まれて馬の背を歩く

アップダウンあり

万三郎を過ぎるとモヤが晴れ、清々しいブナ林

トウゴクミツバツツジあり

アマギツツジあり

ともあれ、天城の花の女王にお目にかかれて光栄です。

この続きはまた明日・・。

2013年5月26日 (日)
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
SHC5月定例山行は、
『石楠花咲く天城を歩こう。』
今年は石楠花シーズンの裏年にあたるそうで花芽が少なく開花も早め。 ギリギリ、最後のシャクナゲが見られました。




「あそこにいっぱい咲いているのにね。」
遠くに咲くシャクナゲに近づけないもどかしさ

登山道脇のやさしい薄桃色の花弁が疲れを癒してくれる。

ヒメシャラやアセビの自然林に囲まれて馬の背を歩く

アップダウンあり

万三郎を過ぎるとモヤが晴れ、清々しいブナ林

トウゴクミツバツツジあり

アマギツツジあり

ともあれ、天城の花の女王にお目にかかれて光栄です。

この続きはまた明日・・。
♪ ~ 2コースで歩く天城山 ・ その3 に続く。
by トンボ






